森林破壊・小学生にできること

森林破壊・小学生にできること
はじめに ~森と私たちのつながり~
みなさんは「森林(しんりん)」と聞くと、どのような景色を思い浮かべるでしょうか。大きな木々が生い茂り、鳥や動物が暮らし、清らかな空気が漂う場所――そんなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
森林は、私たち人間にとって、とても大切な存在です。空気をきれいにし、地球を涼しく保ち、動植物たちの住みかを守り、私たちの生活を支えてくれています。しかし、今、その森林が世界中で急速に失われていることをご存じでしょうか。それを「森林破壊(しんりんはかい)」といいます。
「森林破壊」と聞くと、大人たちや国々の問題だと思ってしまうかもしれません。けれど、実は小学生のみなさんにもできることがたくさんあります。この記事では、まず森林がどんな役わりをしているのかをお話しし、そのうえで森林破壊の原因や現状、そして最後に、小学生のみなさんにできることを一緒に考えてみたいと思います。
第1章 森林ってどんなところ?どんな役わりがあるの?

森林は、ただ木がたくさん生えている場所ではありません。さまざまな命を育む「いのちのゆりかご」ともいわれるほど、多くの役わりを持っています。ここでは、森林の大切な役わりをいくつかご紹介します。
1-1 空気をきれいにしてくれる
木は、太陽の光をあびて「光合成(こうごうせい)」という働きをしています。二酸化炭素(にさんかたんそ)を取り込み、酸素(さんそ)を出してくれるのです。このおかげで、私たちはきれいな空気を吸うことができます。
もし世界の森林がなくなってしまうと、二酸化炭素が増えて地球が暑くなりすぎてしまう「地球温暖化(ちきゅうおんだんか)」が進んでしまうといわれています。
1-2 雨や水をたくわえ、洪水を防ぐ
木の根っこは土をしっかりつかまえて離しません。このおかげで大雨が降っても土砂くずれが起きにくく、川や海がにごるのを防いでいます。また、森は雨水をゆっくりと地面にしみこませ、地下水としてためておきます。そのため、川の水が急に増えたり減ったりするのを防いでくれるのです。
1-3 たくさんの生き物の家
森林には、鳥や虫、動物、植物など、たくさんの生き物たちが暮らしています。日本の森林にも、キツネ、タヌキ、サル、シカなどが住んでいますし、世界にはオランウータンやトラ、ゾウなど、珍しい動物たちも森の中で生きています。
森林が減ってしまうと、こうした生き物たちの住む場所がなくなり、絶滅してしまう恐れがあるのです。
1-4 木材や食べ物の恵み
木は、家具や家、紙など、私たちの生活に欠かせないものを生み出しています。また、森の中には木の実やきのこ、薬の材料になる植物などもあります。森の恵みは、私たちの生活を豊かにしてくれる大切な宝物なのです。
第2章 森林破壊ってなに?どうして起きるの?

では、そんな大切な森林が、なぜ「破壊」されてしまうのでしょうか。次に、森林破壊の原因と現状についてお話しします。
2-1 森林破壊の意味
森林破壊とは、木を切りすぎたり、森を焼いたりして、木や生き物たちの住む場所が失われることをいいます。もちろん、木を切ることが全部悪いわけではありません。家や紙を作るために木を使うのは、人間にとって必要なことです。けれど、大事なのは「森が元に戻るスピードをこえて、木を切りすぎない」ということです。
しかし、世界では今、そのスピードをこえて木がどんどん減ってしまっているのです。
2-2 森林破壊の主な原因
森林破壊には、いくつかの大きな原因があります。
① 農地(のうち)を作るため
世界には、木を切り倒してその場所を畑に変えることがよくあります。特に、アマゾンなどの熱帯雨林(ねったいうりん)では、大豆(だいず)や牛を育てるために、たくさんの木が切られています。
② 木材を売るため
家具や家を作る木材を外国に売るために、森をどんどん切ってしまう国もあります。木を切ること自体は悪いことではありませんが、植え直さずに切り続けると、森は二度と元に戻らなくなってしまいます。
③ 燃料にするため
世界の中には、木を切って燃やし、火をおこして料理をしたり暖まったりしている人々もいます。とても貧しい地域では、木が生活の大切な燃料なのです。でも、使いすぎると森がなくなってしまいます。
④ 開発のため
道路を作ったり、町を広げたりするために、森を切り開くことも森林破壊の原因です。
⑤ 火事や自然災害
人間が火をつけることもありますが、自然に起きる山火事も森林破壊の原因のひとつです。
2-3 森林破壊が進むとどうなるの?
もしも森林破壊がこのまま進んでしまうと、次のようなことが起きるおそれがあります。
- 地球温暖化がさらに進み、世界の気温が上がる
- 洪水や土砂くずれが増える
- 絶滅する動物や植物が増える
- 森で暮らす人々が家を失う
- 私たちが使う紙や木材が手に入りにくくなる
こうした問題は、遠い国の話のように思えるかもしれません。でも、実は私たちの生活ともつながっているのです。
第3章 森林破壊と私たちのくらしの関係
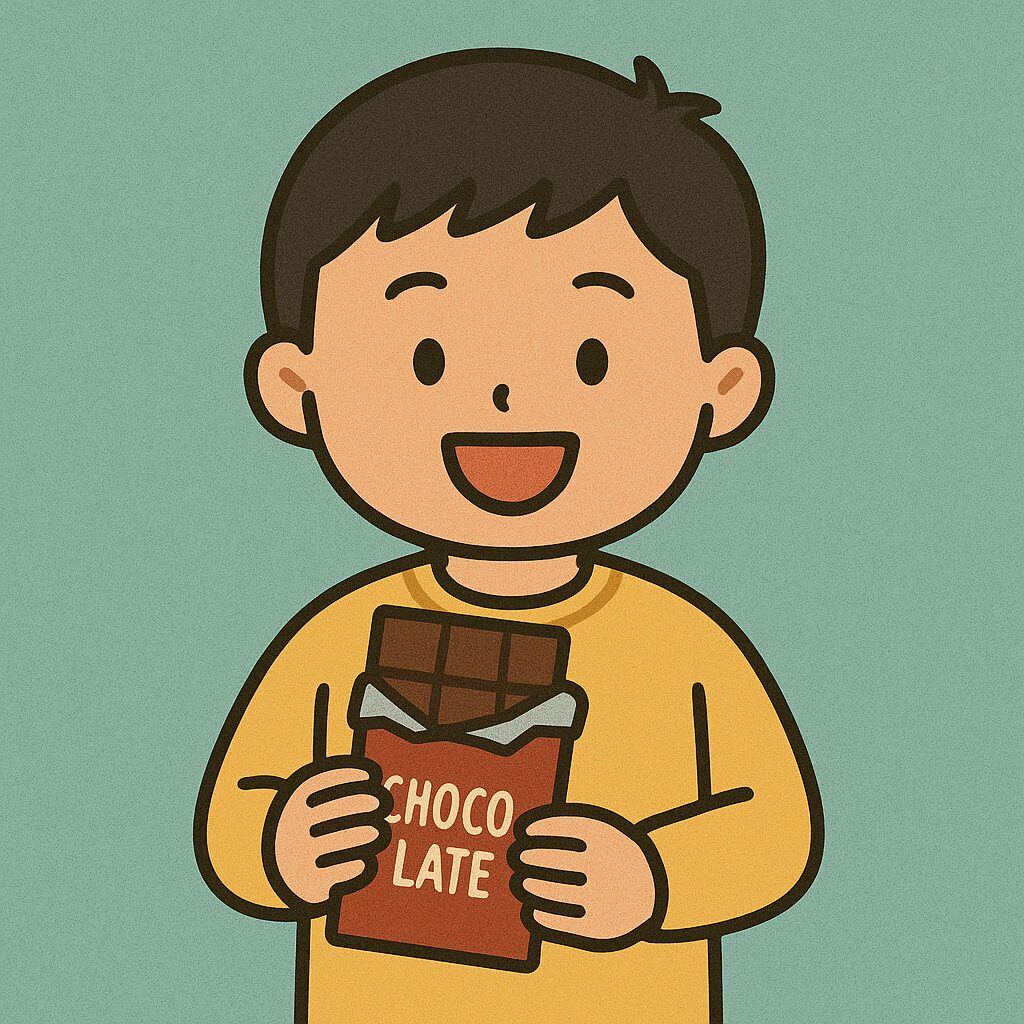
「森林破壊」というと、外国の話や大人たちの問題のように感じるかもしれません。しかし、私たちの身近な生活も、森林破壊とつながっています。
3-1 買い物と森林破壊
スーパーやお店に行くと、いろいろなものが並んでいますね。例えばチョコレートやクッキー、肉、紙など…。実は、その中には、森を切り開いて作られたものもあります。
例えば、
- チョコレート → カカオを育てるために熱帯雨林を切って畑にすることがある
- 牛肉 → 牧場を作るために木を切り倒すことがある
- 紙 → 木を切って作られる
私たちが何気なく買っているものが、どこかの森の木を減らしているかもしれないのです。
3-2 食べ物のむだづかい
食べ物を作るためにも、たくさんの土地が必要です。食べ物を残してしまうと、その分ムダに森を切ることになってしまうこともあります。
「食べ物を残さず食べる」というのは、森を守ることにもつながっているのです。
3-3 紙の使いすぎ
ノートやプリント、ティッシュペーパーなど、私たちはたくさんの紙を使っています。紙を作るためには木が必要です。必要以上に紙を使いすぎると、木がどんどん切られてしまいます。
第4章 小学生にできること
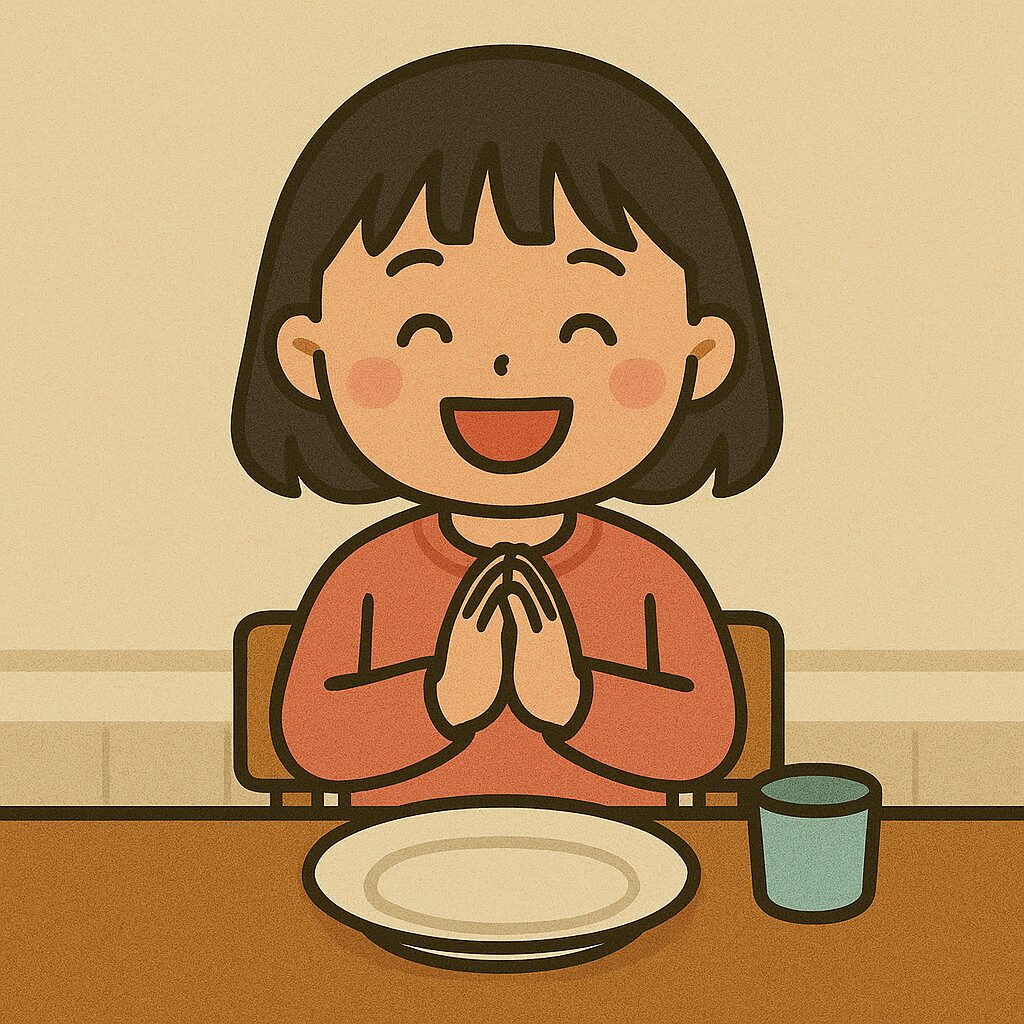
ここまで読んでくれたみなさんの中には、きっと「森林破壊は大変そうだけど、自分に何ができるの?」と思っている人もいるかもしれません。でも、大丈夫です。小学生のみなさんにできることは、実はたくさんあります。ひとつひとつは小さなことでも、みんなで力を合わせれば、森を守る大きな力になりますよ。
4-1 紙を大切に使う
まず、すぐにできるのが「紙を大切に使う」ことです。ノートのページをむだに残さず使い切る、いらないプリントの裏をメモに使うなど、ちょっとした工夫で紙の使いすぎを防ぐことができます。
また、ティッシュペーパーやトイレットペーパーも、必要以上に使わないように気をつけましょう。紙を大事に使うことで、森の木を守ることにつながります。
4-2 食べ物を残さない
食べ物を作るためには、森を切り開いた畑や牧場が使われていることがあります。だから、食べ物を残さず食べることも森を守ることのひとつです。
苦手な食べ物があるときは、少なめによそってもらうなど、自分にできる工夫をしてみましょう。
4-3 森や自然について学ぶ
森のことを知ることは、森を守る第一歩です。図書館で本を読んだり、学校やインターネットで調べたりしてみましょう。また、森に行って自然にふれ合う体験も大切です。
学んだことを家族や友だちに話すことも、とても素敵なことです。みんなが森のことを知れば知るほど、森を大切にする気持ちが広がっていきます。
4-4 森を守る製品をえらぶ
最近では「森林を守るために作られた製品」が増えています。例えば、FSCマークがついた紙や木の製品があります。FSC(エフエスシー)とは「森林を大切にして木を使うしくみ」のことです。このマークがついたものをえらぶことで、森を守る活動を応援できます。
おうちの人と一緒に買い物に行くときに、そうしたマークを探してみるのも楽しいですね。
4-5 ものを大切に使う
おもちゃや文房具、服など、私たちが使うものを作るためには、木やいろいろな資源が使われています。物を大切に長く使うことは、森を守ることにもつながります。
- 壊れたらすぐ捨てずに修理してみる
- いらなくなったものを人にゆずる
- 買うときに「本当に必要か」考える
こうしたことを心がけるだけでも、森の負担は減っていきます。
4-6 声を届ける
大人たちや社会に「森を守りたい」という思いを伝えることも、大切な行動です。たとえば、学校の作文や新聞の投稿で思いを伝えるのも素敵ですし、イベントで森を守る活動に参加するのも良い方法です。
みなさんの声は、大人たちが「もっと森を守らなくては」と考えるきっかけになりますよ。
第5章 世界の人たちの取り組み

みなさんと同じように、世界のたくさんの人たちが森林を守るために努力しています。いくつかの取り組みを紹介しますね。
5-1 植林(しょくりん)の活動
木を切った場所に新しい木を植えることを「植林」といいます。植林は、失われた森を少しずつ取り戻すためにとても大切な活動です。
世界には、ボランティアで木を植える人たちがたくさんいます。日本でも地域ごとに植林活動が行われています。
5-2 森林認証制度
さきほどお話ししたFSCマークのように、「きちんと森を守りながら木を使っている」と認められた製品につけられるマークがあります。これを「森林認証制度(しんりんにんしょうせいど)」といいます。
こうした制度があることで、お店に並ぶ製品の中から、森にやさしいものを選びやすくなっています。
5-3 熱帯雨林を守る国際的な協力
アマゾンなどの熱帯雨林を守るため、国どうしが協力してお金を出し合い、森を保護する活動を支えています。熱帯雨林は世界中の空気や気温を守る大切な場所なので、遠く離れた国も協力して守ろうとしているのです。
5-4 教育やイベント
多くの国で、子どもたちに森の大切さを伝える授業やイベントが行われています。森に出かけて木を調べたり、自然観察をしたりする活動は、子どもたちが森をもっと身近に感じるために大切な取り組みです。
第6章 まとめ ~森を守る未来へ~
みなさん、ここまで長いお話を読んでくれてありがとうございました。最後に、もう一度大事なことをまとめてみましょう。
- 森は、空気をきれいにしたり、動物たちの住む場所になったり、地球の環境を守ったりする大切な場所です。
- でも、世界では木を切りすぎたり、森を焼いて畑にしたりして、森がどんどん減っています。これを「森林破壊」といいます。
- 森林破壊が進むと、地球温暖化が進み、動物が絶滅したり、自然災害が増えたりします。
- 小学生のみなさんにもできることがたくさんあります。たとえば、紙や物を大切に使うこと、食べ物を残さないこと、森について学ぶことなどです。
森林を守るための行動は、小さなことの積み重ねです。でも、その小さな行動が集まると、きっと森を守る大きな力になります。
森は私たち人間だけのものではありません。動物たちや未来の子どもたちも、豊かな森を必要としています。だからこそ、今できることをひとつずつやっていくことがとても大事なのです。
ぜひ、みなさんも森のことを家族や友だちに話してみてください。そして「どうしたら森を守れるかな?」と、一緒に考えてみてくださいね。










