質量保存の法則・身近な例

質量保存の法則・身近な例
みなさんは「質量保存の法則(しつりょうほぞんのほうそく)」という言葉を聞いたことがありますか?この法則は、中学2年生で理科の授業に出てくる大切な考え方です。でも、ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんね。
実はこの「質量保存の法則」は、私たちの身のまわりでもよく見られるルールなのです。この記事では、なるべくやさしい言葉で、質量保存の法則の意味と、質量保存の法則の身近な例(生活の中でどのようにあらわれているか)を紹介していきます。
質量保存の法則ってなに?
まずは「質量保存の法則」とは何かを確認しましょう。
🔬質量保存の法則とは?
「化学変化が起こっても、物質の全体の質量は変わらない」という法則です。
たとえば、ある物質が燃えたり、酸化したり、分解したりして別の物質に変わったとしても、もとの物質の重さ(質量)と、できた物質の重さを合わせたら、ぜんぶで同じ重さになるということです。
これは、フランスの化学者アントワーヌ・ラヴォアジエによって、1700年代に発見されました。
どうして大事なの?
化学の世界では、物質がどのように変化するかを考えるときに、「どれくらいの量(質量)の物質が使われ、どれくらいできるか」を知ることがとても大切です。
そのため、この法則は、化学の基本中の基本とも言えるのです。
質量保存の法則のしくみをイメージで理解しよう
たとえば、料理をしているときのことを思い出してください。
あなたがお鍋で野菜スープを作るとき、にんじんやたまねぎ、水、スープのもとなどを入れますよね。煮込んでいくと、見た目や形は変わっていきますが、ふたをしておけば、中に入っているすべてのものの重さは変わりません。
これが「質量保存の法則」の考え方に近いのです。
身近な例をたくさん紹介!
ではここからは、私たちが普段の生活で体験している「質量保存の法則」の例をいくつか紹介します。
① 食塩水をつくる実験

理科の授業などで、水100gに食塩10gをとかして食塩水をつくることがありますね。
この時、元の水と食塩の質量を合わせると「100g + 10g = 110g」となります。そして、できた食塩水をはかると、ちゃんと110gになります。
食塩は水にとけて見えなくなりますが、なくなったわけではありません。ちゃんと水の中に存在しているのです。
これがまさに質量保存の法則です。
② ペットボトルに炭酸を入れるとき

炭酸飲料は、ペットボトルの中に二酸化炭素(CO₂)がとけています。ふたを開けると「プシュー」と音がして、気体が出てきますよね。
ふたを開ける前と後で、飲み物の味や泡立ちが変わるのは、二酸化炭素が抜けるからです。そして、ふたを開ける前と後でペットボトル全体の重さを量ると、ふたを開けた後の方が軽くなっています。
これは、ボトルの中にとけていた二酸化炭素が空気中に出て行ったからです。重さが減ったのではなく、「場所が変わった」だけ。全体の質量は変わっていません。
③ ろうそくの燃焼

ろうそくに火をつけると、少しずつ短くなっていきますよね。「あれ?ろうそくって燃えると軽くなるのかな?」と思うかもしれません。
実際には、ろうそくのロウが空気中の酸素と反応して、二酸化炭素や水蒸気に変わっています。このときに出ていった気体もちゃんと重さを持っています。
もし燃焼中のろうそくをふたつきの容器の中で燃やして、気体も逃がさずに量をはかれば、はじめとあとでの質量は変わらないことが分かります。
④ 錆びたくぎ

鉄のくぎが長い間空気にふれていると、茶色くサビていきますよね。このとき、「サビて軽くなったのかな?」と思うかもしれませんが、逆です。
サビは鉄と空気中の酸素が結びついたものなので、重さはむしろ増えます。でも、鉄だけの重さではなく、「鉄+酸素」の重さになるので、ぜんたいとしてはバランスが取れています。
⑤ お菓子作り
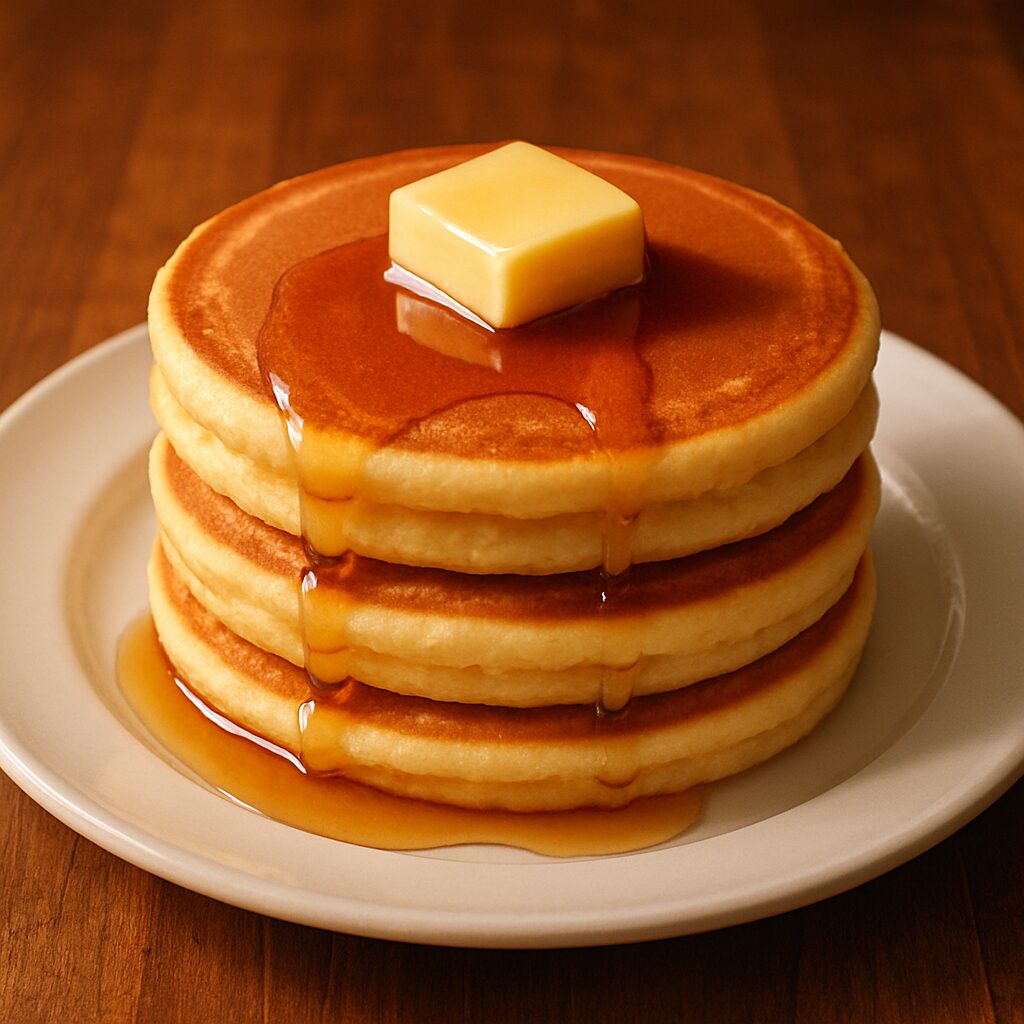
ホットケーキを作るとき、小麦粉、卵、牛乳、砂糖、ベーキングパウダーなどを混ぜて焼きますね。すると、ふっくらとふくらんで、見た目も香りも変わります。
「焼いたら軽くなった!」と思うことがあるかもしれませんが、それは水分が蒸発したり、ガスが出て空気中に逃げたからです。
すべての出入りを計算すれば、材料の重さと、できあがったホットケーキ+蒸発した水蒸気や気体の重さを合わせると、最初の材料の重さと同じになるはずです。
⑥ 鍋で煮物をするとき

カレーやシチューを作っていて、ふたをして煮込むと、水分がなかなか減りません。重さも変わりません。でも、ふたをしないで長時間煮込むと、水分が蒸発して軽くなります。
このとき、「質量が減った」と思うかもしれませんが、実際には水蒸気として空気中に逃げていっただけ。部屋全体をはかれば、質量はちゃんと保存されています。
なぜ質量は保存されるの?
質量保存の法則が成り立つ理由は、「原子(げんし)」が関係しています。
すべての物質は、「原子」とよばれるとても小さな粒でできています。化学変化が起きるとき、この原子がくっついたり、組みかえられたりしますが、「原子そのもの」がなくなったり、新しく生まれたりはしません。
だから、化学変化の前と後で、原子の数は同じ。つまり、質量も変わらないのです。
じゃあ、どうして「軽くなった」と感じることがあるの?
これはとてもよくある疑問です。
例えば、キャンプでたき火をすると、木が燃えて灰になりますよね。「あんなにたくさんあった木が、こんなに少しの灰になった。だから軽くなったんだ」と思うかもしれません。
でも実は、燃えた木は空気中の酸素と反応して、二酸化炭素や水蒸気として空気中に出て行ってしまったのです。だから目には見えないけれど、その気体たちもちゃんと質量を持っています。
「見えなくなった=なくなった」ではないのですね。
実験で確かめてみよう
質量保存の法則を体験するためには、いくつかの簡単な実験があります。たとえば:
🔹 ビニール袋にクエン酸と重そう(炭酸水素ナトリウム)を入れて水を加え、密閉して反応させる。反応前後で袋ごと重さをはかる。
🔹 気体の発生や水の蒸発をふたつきの容器で防ぎながら、前後の重さを比べる。
このようにすれば、質量保存の法則がちゃんと成り立っていることが分かります。
まとめ
✅ 質量保存の法則とは?
化学変化の前後で、全体の質量(重さ)は変わらないというルール。
✅ なぜ?
物質は原子でできていて、その原子の数は変化しないから。
✅ 身近な例
- 食塩水
- ペットボトルの炭酸
- ろうそくの燃焼
- サビたくぎ
- お菓子づくり
- 煮物
質量保存の法則は、教科書の中だけのものではありません。毎日の生活の中でもよく見かけることができます。
科学は、身近なものの見方を少し変えてくれる力があります。「どうしてこうなるんだろう?」と疑問を持ち、考えてみることが、理科を楽しむ第一歩です🌱










