南海トラフ地震・生き残る地域
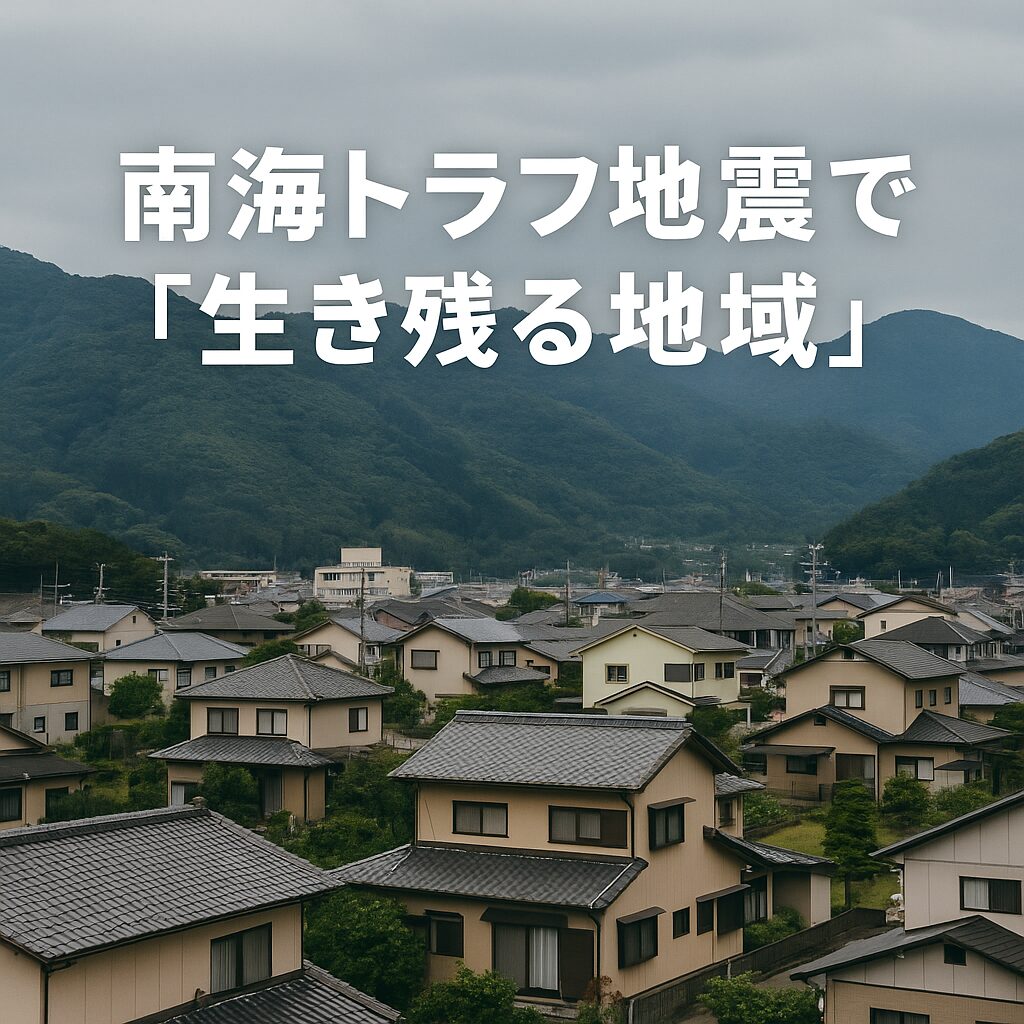
南海トラフ地震・生き残る地域
南海トラフ地震──。この言葉は、私たち日本に住む者にとって、常に心の片隅にある不安の種かもしれません。M8〜M9クラスの巨大地震、それに伴う津波、そして長期にわたるライフラインの寸断。想像を絶する被害が予測されています。
しかし、私たちはただ恐れているだけでいいのでしょうか? いえ、そんなことはありません。適切な知識と備えがあれば、被害を最小限に抑え、「生き残る」可能性を飛躍的に高めることができます。
この記事では、「南海トラフ地震で生き残る地域」というテーマで、具体的な県名や地域名にも触れながら、災害リスクを考慮した地域選びのヒントと、私たち一人ひとりができる備えについて掘り下げていきます。ただし、**「絶対的に安全な場所は存在しない」**ことを前提に、あくまで「比較的被害が少ないと想定される地域」という視点でお伝えします。最終的には、ご自身の居住地域のハザードマップを必ず確認してくださいね。
南海トラフ地震とは?
南海トラフは、静岡県沖から九州沖にかけて延びる海底の溝(トラフ)のこと。ここでは、フィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込むことで、巨大な地震が周期的に発生してきました。
歴史を振り返ると…
- 1707年:宝永地震
- 1854年:安政東海・南海地震
- 1944年:昭和東南海地震
- 1946年:昭和南海地震
これらの大地震はいずれも南海トラフ沿いで発生しています。次の南海トラフ地震は「いつ起きてもおかしくない」と専門家は指摘しており、切迫度は高まるばかりです。
「生き残る地域」とは、複合的なリスクを考慮した場所
「生き残る地域」とは、単に「揺れが少ない場所」だけを指すわけではありません。以下の5つの要素を総合的に判断することが重要です。
- 揺れにくさ(地盤の強固さ): 地震の揺れによる建物の倒壊や液状化のリスクが低いか。
- 津波のリスクの低さ: 海抜が高く、津波浸水想定区域外であるか。
- ライフラインの復旧力・代替手段の確保: 電気、ガス、水道などのインフラが比較的早く復旧するか、代替手段があるか。
- 災害時の医療・救援体制: 災害拠点病院へのアクセスや、救援物資の供給ルートが確保されているか。
- コミュニティの防災意識と共助の精神: 地域の住民同士が助け合える体制が整っているか。
これらの要素を踏まえて、具体的な地域を見ていきましょう。
津波リスクが低く、揺れも比較的少ない内陸の県
南海トラフ地震の震源域から離れており、かつ海に面していない内陸の県は、津波による直接的な被害を受ける心配がなく、揺れも比較的少ないとされています。
- 長野県: 南海トラフのプレート境界から距離があり、内陸のため津波の影響もありません。ただし、活断層による直下型地震のリスクは考慮が必要です。
- 岐阜県: 同様に内陸に位置し、南海トラフの直接的な影響は小さいとされます。山間部では土砂災害のリスクに注意が必要です。
- 滋賀県: 琵琶湖を挟んでいますが、南海トラフの震源からは離れており、揺れや津波のリスクは比較的低いとされています。
これらの県は、内閣府などの被害想定でも、揺れや津波による直接的な被害が比較的少ない地域として挙げられることが多いです。ただし、内陸部だからといって安心は禁物。ご自身の地域の活断層情報や、土砂災害ハザードマップは必ず確認しましょう。
震源から遠く、揺れが比較的小さい北日本の県
南海トラフ地震の震源からはるか北に位置する県では、地震のエネルギーが減衰し、揺れの影響が比較的少ないと予測されています。
- 北海道
- 青森県
- 秋田県
- 山形県
- 岩手県
- 福島県(特に内陸部)
これらの地域では、南海トラフ地震による揺れは比較的軽微であると考えられます。しかし、太平洋沿岸部では、遠方であっても津波が到達する可能性はあります。特に、東日本大震災の教訓からも、津波への備えは非常に重要です。海沿いに住む場合は、津波ハザードマップを徹底的に確認し、高台への避難経路を把握しておきましょう。
大都市圏における「高台」や「強固な地盤」のエリア
太平洋沿岸の大都市圏に住んでいる場合でも、地域内には比較的安全な場所が存在します。これは、高台に位置している、あるいは古くからの強固な地盤の上にあるといった特徴を持つ場所です。
- 東京都(特に武蔵野台地の上、例えば世田谷区、杉並区、目黒区、練馬区などの一部)
- 東京23区内でも、多摩川や荒川沿いの低地、湾岸の埋立地は液状化や津波のリスクが高いとされています。一方で、武蔵野台地と呼ばれる高台地域は、比較的安定した地盤で揺れに強く、津波の影響も受けません。しかし、都心へのアクセスなどを考慮すると、通勤圏内でそうした地域を見つけることが重要です。
- 大阪府(特に上町台地周辺、例えば大阪市天王寺区、阿倍野区、住吉区などの一部)
- 大阪平野の東部にある南北に伸びる上町台地は、古くから強固な地盤として知られ、南海トラフ地震の揺れや液状化のリスクが低いと予測されています。大阪湾に面した埋立地や淀川沿いの低地に比べて、安全性が高いと言えるでしょう。また、北部の吹田市や豊中市の一部も高台が多く、比較的被害が少ないとされています。
- 愛知県(名古屋市東部や北部の一部、例えば守山区、名東区などの丘陵地)
- 名古屋市中心部から東部、北部にかけて広がる丘陵地帯は、地盤が比較的安定しており、揺れや液状化のリスクが低いとされています。名古屋港周辺の埋立地や河川沿いの低地に比べると、安全性が高いと言えます。
これらの地域は、大都市の中では比較的リスクが低いとされますが、活断層の有無、個々の地盤状況、そして津波の浸水想定区域など、詳細なハザードマップでご自身の住む場所の具体的なリスクを必ず確認してください。
地域の防災力とコミュニティの強さも重要
どの地域に住むかという物理的な条件だけでなく、その地域の「防災力」も非常に重要です。
- 自治体の防災体制: 防災計画がしっかりしているか、避難所の運営や物資備蓄体制はどうか。
- ライフラインのレジリエンス: 電力や通信のインフラが分散されているか、代替手段の確保が進んでいるか。例えば、静岡県や高知県など南海トラフ地震の被害が特に懸念される地域では、行政や企業が連携して防災対策やインフラ強靭化に力を入れています。
- 住民の防災意識と共助: 自主防災組織が活発で、地域の訓練参加率が高いか。いざという時に住民同士が助け合える体制が整っている地域は、復旧も早く、生存率も高まります。これは特定の県名や市名で一概には言えませんが、移住を検討する際には、地域の自治会活動や防災イベントの有無などを確認してみるのも良いでしょう。
地域選びは「複合的なリスク評価」と「個人の備え」から
「南海トラフ地震で生き残る地域」という問いに対する明確な「この地域!」という答えを出すことは困難です。しかし、この記事で挙げたような視点から、ご自身のライフスタイルや家族構成に合わせて、リスクを複合的に評価し、より安全性の高い地域を選ぶことは可能です。
そして最も重要なことは、**「どの地域に住んでいても、自分自身と家族の命を守るための備えを怠らないこと」**です。
- 家具の固定: 最も基本的なことですが、命を守ります。
- 非常用持ち出し袋の準備: 3日分以上の食料、水、簡易トイレ、常備薬、懐中電灯などを準備しましょう。
- 家族との連絡手段・避難場所の確認: 災害伝言ダイヤルや集合場所などを共有しておきましょう。
- 地域のハザードマップの確認と避難経路の把握: 定期的に確認し、実際に歩いてみるなど、具体的な訓練を行いましょう。
南海トラフ地震は、いつか必ず起こると言われています。しかし、必要以上に恐れるのではなく、冷静にリスクを評価し、適切な備えをすることで、私たちは「生き残る」ための力をつけることができます。
「安全な地域に住めば大丈夫」ではない
ただし、いくら被害想定が少ない地域でも油断は禁物です。
- 南海トラフ地震は広範囲にわたり揺れる可能性が高い
- ライフラインの寸断は内陸でも発生しうる
- 広域避難者が流入する可能性も大
つまり 「どこに住むか」だけでなく、日頃の備えが生死を分ける のが現実です。









