ジュゴン

ジュゴン
🌊ジュゴンの生態・歴史・保護の現状まで解説
海の生き物の中でも、その優雅な泳ぎと穏やかな表情で知られる「ジュゴン」。人魚伝説のモデルともいわれるこの生き物は、実は絶滅の危機に瀕しています。本記事では、ジュゴンの生態や進化の歴史、日本や世界での分布、そして現在の保護活動まで、くわしく丁寧に解説します。
🐋1. ジュゴンってどんな生き物?
▶ 学名と分類
ジュゴンは哺乳類で、海牛目(カイギュウ目)・ジュゴン科に属しています。学名は「Dugong dugon(ジュゴン・ドゥゴン)」です。ジュゴン科は現在、ジュゴン1種しか生存しておらず、仲間だったステラーカイギュウはすでに絶滅しています。
▶ 外見の特徴
- 体長:約2.5〜3.5メートル
- 体重:約300〜500キログラム
- 皮膚:灰色〜茶色がかった色
- 尾:イルカのような三日月型(マナティーは丸い尾)
丸く優しい目、なめらかな流線型の体、草を食べる姿からは、まるで海の中の草食動物といった印象を受けます。
🌱2. ジュゴンの食生活と生態
▶ 食性:海草(うみくさ)を主食とする「海の草食動物」
ジュゴンは完全な草食性で、海草(seagrass)を主食としています。サンゴ礁の近くの浅い海に生える海草を、下向きの口で掘り起こすようにして食べます。これにより海草が再生しやすくなり、海の生態系において「庭師」としての役割も果たしているのです。
▶ 行動パターン
- 昼夜問わず行動するが、夜間の活動がやや活発
- 単独、または2〜3頭で行動することが多い
- 年間数百kmも移動することがあり、広範囲に海草を求める
▶ 繁殖と子育て
ジュゴンは哺乳類なので、赤ちゃんは母乳で育ちます。妊娠期間は約13ヶ月と長く、1度に1頭しか出産しません。数年に一度しか子どもを産まないため、個体数の回復には非常に時間がかかるのです。
🧬3. 進化の歴史と人魚伝説との関係
ジュゴンは、約5000万年前に陸上の草食動物から進化したと考えられています。その祖先はゾウに近い存在で、のちに水中生活に適応して現在の姿となりました。
▶ 人魚伝説の由来?
昔の船乗りたちは、ジュゴンやマナティーを遠目に見て「人魚」と思ったという説があります。特に授乳中の母ジュゴンを遠くから見ると、女性が赤ん坊を抱いているように見えたため、そうした伝説が生まれたのではないかと考えられています。
🗾4. 世界と日本での分布
▶ 世界の分布
ジュゴンは熱帯から亜熱帯の沿岸に生息しており、インド洋から西太平洋にかけての100以上の国・地域に分布しています。代表的な生息地には、以下のような場所があります。
- オーストラリア北部(特にグレートバリアリーフ)
- フィリピン
- タイ湾
- マダガスカル近海
- サウジアラビア沿岸
▶ 日本での生息地
かつては本州南部から琉球諸島全域にかけて広く分布していましたが、現在確認されているのは沖縄本島周辺のごく一部のみです。
- 沖縄県名護市の辺野古沖
- 宮古島・石垣島では過去に目撃例あり
⚠️5. 絶滅危惧種としての現状
▶ IUCNによる分類
国際自然保護連合(IUCN)はジュゴンを「絶滅危惧種(Vulnerable)」に指定しています。特に日本周辺の個体群は、環境省のレッドリストで「絶滅のおそれのある地域個体群」に指定されています。
▶ 主な脅威
- 海草藻場の消失(埋立・護岸工事による)
- 漁業による混獲
- 船舶との衝突
- 音響によるストレス(軍事演習など)
- 観光開発による環境破壊
🛡️6. 世界と日本の保護活動
▶ 国際的な取り組み
- CITES(ワシントン条約)附属書Ⅰに掲載:国際取引は禁止
- オーストラリア:保護区の指定、海草藻場の復元
- フィリピン:ジュゴン保護法の制定とコミュニティ参加型保護
▶ 日本での取り組み
- 辺野古周辺での環境アセスメントの実施(基地建設問題と関連)
- 沖縄美ら海水族館などによる啓発活動
- 環境NPOによる観察・調査・教育活動
🤔7. 辺野古問題とジュゴン保護の葛藤
沖縄県辺野古地区では、米軍基地移設のための埋立工事が進行しています。この地域はジュゴンの重要な海草藻場がある場所であり、保護団体や研究者からは「重大な生息地破壊」として強い懸念が表明されています。
▶ 法廷闘争にも発展
ジュゴンの存在を根拠に、アメリカでは環境保護団体が国防総省を提訴するなど、国際的な注目も集まりました。アメリカの「国家歴史保存法(NHPA)」に基づき、ジュゴンが「文化遺産」として扱われるケースもありました。
🧠8. なぜジュゴンは守らなければならないのか?
▶ 生態系のキーストーン種
ジュゴンが食べる海草は、海の二酸化炭素を吸収する大切な存在です。ジュゴンが海草を定期的に食べることで、藻場が健康に保たれ、生物多様性が維持されます。
▶ 人間との共存モデルとして
人類の開発と自然との共存は、21世紀の大きな課題です。ジュゴンの保護活動は「経済開発 vs 環境保護」の典型的な問題であり、その在り方を見直す機会を私たちに与えてくれます。
🧒9. 教育・観光・地域との関わり
▶ 教育的価値
ジュゴンは環境教育のシンボル的存在でもあります。海の保護、生物多様性、持続可能な開発について考えるきっかけを与えてくれます。
▶ エコツーリズムとしての活用
ジュゴンを野生で観察できる観光プログラムは、オーストラリアやフィリピンで人気を博しています。地域経済と保護が両立する仕組みとして注目されています。
🧭10. 私たちにできること
- 海洋プラスチックゴミを減らす
- サンゴ礁や藻場を壊さない行動を取る
- ジュゴン保護の募金や署名に協力する
- 保護活動を行っているNPOや自治体の情報を発信する
- 教育現場でジュゴンについて取り上げる
📝11. まとめ:ジュゴンの未来を守るために
ジュゴンは人類の開発によって静かに追い詰められている、海の優しい巨人です。その存在は、海の生態系の健全さを示すバロメーターであり、私たち自身が自然とどう向き合うかを問われています。
保護の鍵は「知ること」、そして「行動すること」。遠い存在と思わず、ジュゴンの未来が私たちの選択にかかっているという意識を、今こそ持つべき時です。

🐠Q1. 日本ではジュゴンはどこで見られますか?
🅰️現在、日本国内では、三重県・鳥羽水族館がジュゴンを飼育・展示している唯一の施設です。
- 水族館では「セレナ」というメスのジュゴンを長年にわたって飼育しており、世界最長の飼育記録を更新中です。
- また、鳥羽水族館は日本国内で飼育種類数が最も多く(約1,200種)、ジュゴンの展示も含めてその特徴となっています。
したがって、「日本国内でジュゴンを見たい」という方には、鳥羽水族館が現時点で唯一の選択肢です。
🐋Q2. ジュゴンとマナティーとの違いは何ですか?
🅰️以下のように、分類・生息地・外見などに違いがあります:
| 比較項目 | ジュゴン | マナティー |
|---|---|---|
| 科 | ジュゴン科 | マナティー科 |
| 尾の形 | イルカのような三日月型の尾 | 丸いしゃもじ型の尾 |
| 主な生息地 | インド洋〜西太平洋(日本含む) | アマゾン川流域、大西洋沿岸など |
| 食性 | 海草を主食 | 海草や淡水植物なども食べる |
| その他特徴 | 顔は下向き、体型は平たく草食性に特化 | 顔の位置は前方 |
このような外見や生息地の違いに注目すると、両者を見分けやすくなります。
🐠Q3. ジュゴンの現在の数(個体数)は?
🅰️世界全体の現在のジュゴンの個体数は、正確な調査が困難であるため推定値にとどまりますが、約 85,000〜100,000 頭 と考えられています。
地域的には、以下のように分布しています:
- オーストラリア北部(シャーク湾〜モートン湾)には約 10,000 頭。
- ペルシャ湾(アラビア湾)には約 5,800~7,300 頭。
- その他、紅海:約 2,000 頭、ニューカレドニア:約 898 頭、モザンビーク:約 300 頭 。
- マレーシア東部(サバ州・サラワク州):688~1,376 頭(2009年推定)。
🐋Q4. ジュゴンの日本での生息数は?
🅰️日本国内、とくに沖縄県周辺海域でのジュゴン個体数(生息数)は、極めて少なく、数頭~十頭程度と推定されています。
- 環境省や沖縄県による調査では、「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い」とされ、**絶滅危惧ⅠA類(CR)**に指定されています。
- 日本生態学会などの保全の要望書では、「現在その生息数は10 頭程度にすぎない」とも報告されていま。
- 2019年以降は正式な生息確認例がなく、DNA分析や潜水・目撃調査などが続けられているものの、生息個体の数は極めて少数と推定されます
🌟ジュゴンに関するトリビア7選
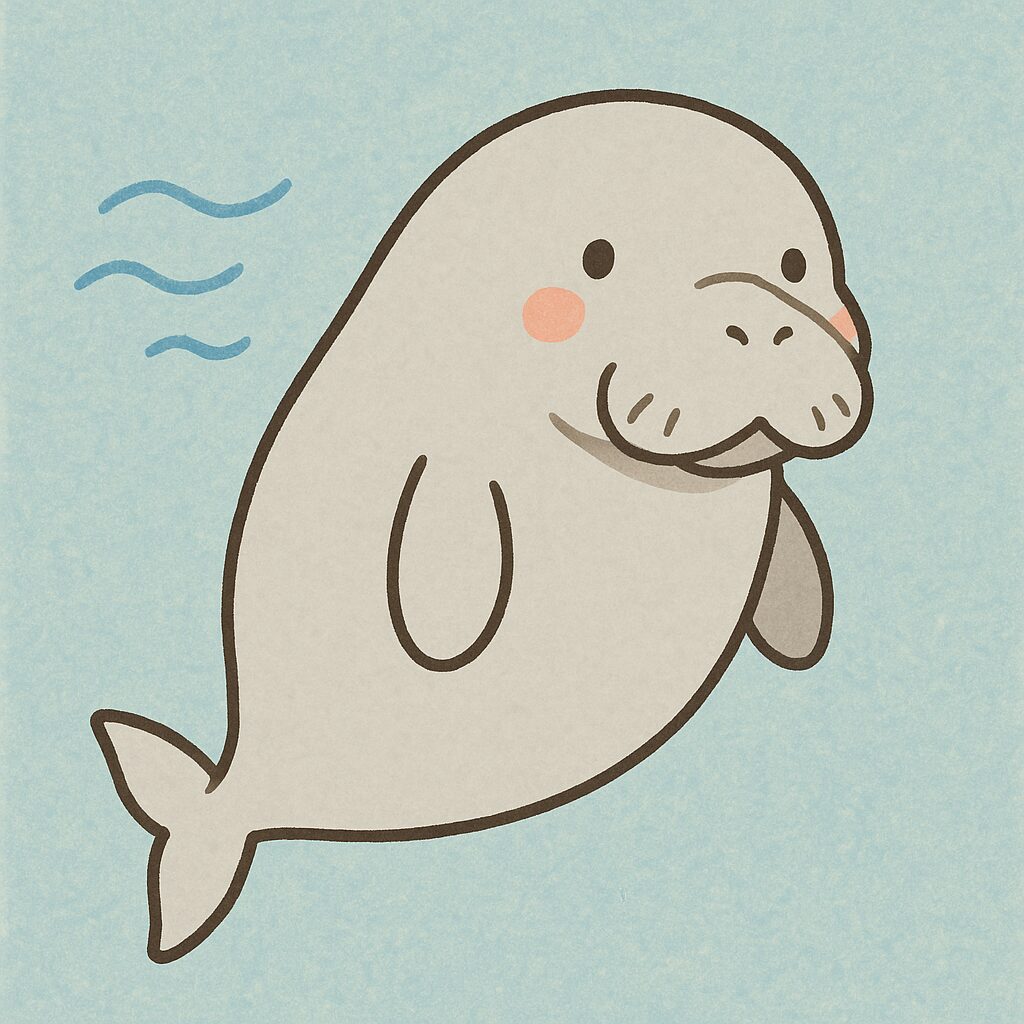 🧜♀️1. 人魚伝説のモデルとされている
🧜♀️1. 人魚伝説のモデルとされている
ジュゴンは、古代の船乗りたちが「人魚(マーメイド)」と見間違えたと言われています。特に、赤ちゃんに授乳している姿が女性のように見えたという説があります。ちなみに「ジュゴン(dugong)」という名前も、マレー語で「人魚」を意味する「duyung」に由来しています。
🇯🇵2. 日本の沖縄には「ジュゴン伝説」がある
沖縄県には、ジュゴンが海の神の使いとして崇められていたという伝説があり、かつては「ジュゴンを殺すと災いが起こる」と信じられていました。今でも一部の地域では、ジュゴンにまつわる歌や民話が残っています。
🐾3. 世界でジュゴンが見られる水族館は非常に少ない
ジュゴンの飼育はとても難しく、世界中でもごくわずかしか飼育されていません。日本では三重県・鳥羽水族館が唯一のジュゴン飼育施設で、そこで飼われている「セレナ」は世界最長飼育記録を更新中です。
🍴4. ジュゴンは1日に約30kgの海草を食べる
ジュゴンは、1日に自分の体重の約10分の1もの海草を食べるといわれています。特に好きなのは「ウミヒルモ」という種類の海草で、これを掘り起こしてムシャムシャ食べる様子は「海の草食牛」とも呼ばれるほど。
🧬5. ゾウの親戚である
ジュゴンの最も近い陸上の親戚は「ゾウ」です。どちらも約5000万年前の共通祖先から進化したと考えられており、ジュゴンの前足の骨をX線で見ると、人間の腕やゾウの前足と非常によく似た構造になっています。
🕊6. ジュゴンはとても穏やかで人懐っこい性格
ジュゴンは非常におとなしく、攻撃性がほとんどありません。人間に対しても好奇心を示すことがあり、オーストラリアやフィリピンでは、ダイバーに近寄ってくるジュゴンの姿が観察されています。
🐢7. 海の環境を「耕す」生き物
ジュゴンは海草を食べるとき、根っこごと引き抜いて食べるため、海底に「トレンチ(溝)」ができます。これがまるで畑を耕すような働きをし、海草の再生を促したり、他の小さな生物の生息環境を作り出したりしています。ジュゴンは「海の庭師」とも呼ばれます。
🎁おまけ:ジュゴンの鳴き声は「ピィー」「キュッ」
ジュゴンは意外にもさまざまな音を発します。人間の耳にも聞こえる音で、「ピィー」や「キュッ」といった可愛らしい声で仲間とコミュニケーションを取ります。鳥羽水族館では、飼育員との音声によるやりとりも報告されています。









