遺伝子組み換え食品・一覧

遺伝子組み換え食品・一覧
遺伝子組み換え食品の包括的リストとその多角的側面
はじめに:遺伝子組み換え食品(GMO)とは?
本記事のテーマは遺伝子組み換え食品の一覧です。
遺伝子組み換え食品(Genetically Modified Organisms, GMOs)とは、特定の目的のために生物の遺伝子を操作する技術、すなわち遺伝子組み換え技術を用いて作られた食品を指します。この技術は、他の生物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、その性質を持たせたい植物などに組み込むことで、従来の品種改良では困難だった特性を付与することを可能にします。
遺伝子組み換え技術の基本と目的
遺伝子組み換え技術の目的は多岐にわたります。例えば、特定の除草剤に耐性を持たせることで雑草管理を容易にしたり、特定のウイルス病に強い作物を作り病害による収量減少を防いだり、あるいは天然添加物の代替となる物質を安定的に供給したりすることが挙げられます。この技術は、単に特定の形質を付与するだけでなく、農業生産における具体的な課題解決を目指しています。
なぜGM食品が開発されるのか:その背景とメリット
遺伝子組み換え技術は、従来の交配による品種改良に比べて、はるかに短い時間で目的の性質を持った品種を得ることを可能にします。また、種の壁を越えて異なる生物間でも遺伝子を挿入できるため、農産物の改良範囲を大幅に拡大できるという特徴があります。この効率性とスピードは、農業の生産性向上とコスト削減に大きく貢献します。
効率的な品種改良は、より低コストで育てやすく、収量の多い品種の開発につながります。農家にとっては、安定的な収量が得られるようになり、農薬の費用や防除作業自体を減らせるため、低コスト化・省力化に貢献するという具体的な恩恵があります。このように、遺伝子組み換え技術の主要な推進力は、農業生産における効率性の向上とコストの削減にあると言えます。これは、より少ない投入でより多くの生産を可能にするという、農業経済学的な合理性を追求した結果です。
さらに、品種改良のスピードが上がることで、増大する世界人口への食料供給や、貧困や飢餓に苦しんでいる人々を助けられる可能性も高まると考えられています 3。この技術は、単なる商業的な利益追求だけでなく、世界の食料安全保障と持続可能性といった、より広範なグローバルな社会課題解決への潜在的な貢献も目的として開発が進められてきました。
世界で商業化されている主要な遺伝子組み換え作物一覧

遺伝子組み換え作物の商業栽培は1996年に開始されて以来、世界中で急速に栽培面積を伸ばしてきました 。現在、世界中で最も広く栽培されている遺伝子組み換え作物は、ダイズ、トウモロコシ、ワタ、ナタネなどであり、特に除草剤耐性品種と害虫抵抗性品種、あるいはそれらを組み合わせたスタック品種が最も利用されています。
2024年現在、遺伝子組み換え作物は世界27カ国で合計2億980万ヘクタール以上の農地で栽培されています。特に北米および南米の国々において大規模に栽培されていますが、ヨーロッパ、アジア、オセアニアの国々でも栽培が行われています。商業栽培が開始された当初は先進工業国が大部分を占めていましたが、現在では発展途上国における栽培面積が先進工業国を上回っています。
遺伝子組み換え作物の商業化は、農業における主要な課題解決に集中的に焦点を当ててきました。除草剤耐性や害虫抵抗性といった特性がGM作物の過半を占め、ダイズ、トウモロコシ、ワタ、ナタネといった基幹作物の栽培面積が大きいことは、世界中の農家が直面する最も普遍的でコストのかかる問題(雑草管理と害虫被害)を効率的に解決することに技術開発が集中してきたことを示しています。この集中は、技術の迅速な普及と経済的効果の最大化を狙った戦略的な選択であったと考えられます。
以下に、遺伝子組み換え食品の一覧 (主要な遺伝子組み換え作物とその主な特性、および開発目的をまとめた表)を示します。
表1:主要な遺伝子組み換え作物とその主な特性:
| 作物名 | 商業化品種数(判明している場合) | 主な特性 | 開発目的/利点 |
| ダイズ | 29種類 | 除草剤耐性、害虫抵抗性、高オレイン酸形質、ステアリドン酸産生 | 雑草管理の効率化、害虫被害の軽減、健康志向の食用油生産 |
| トウモロコシ | 215種類 | 害虫抵抗性、除草剤耐性、高リシン形質、乾燥耐性、耐熱性α-アミラーゼ産生、生産性向上9 | 害虫被害の軽減、雑草管理の効率化、飼料価値向上、過酷な環境下での栽培、収量安定化 |
| ワタ | 48種類 | 害虫抵抗性、除草剤耐性 | 害虫被害の軽減、雑草管理の効率化、農薬使用量の削減 |
| ナタネ | 24種類 | 除草剤耐性、雄性不稔性、稔性回復性、DHA産生、EPA産生 | 雑草管理の効率化、ハイブリッド種子生産効率化、健康志向の食用油生産 |
| テンサイ | 3種類 | 除草剤耐性 | 雑草管理の効率化、生産コスト削減 |
| ジャガイモ | 12種類 | 害虫抵抗性、ウイルス抵抗性、疫病抵抗性、アクリルアミド産生低減、打撲黒斑低減 | 病害虫被害の軽減、加工食品の安全性向上、品質保持 |
| アルファルファ | 5種類 | 除草剤耐性、低リグニン | 雑草管理の効率化、飼料の消化性向上 |
| パパイヤ | 1種類 | ウイルス抵抗性 (パパイヤリングスポットウイルス) | 壊滅的なウイルス病からの産地保護、安定供給 |
各作物の詳細
- 大豆 (Soybeans)
日本で流通している遺伝子組み換え大豆は29種類と報告されており(2023年3月24日現在)、その多くは除草剤耐性遺伝子が付与されたものです。その他にも、害虫抵抗性、高オレイン酸形質、ステアリドン酸産生などの特性を持つ品種が開発されています。世界で栽培されているダイズのおよそ7割がGM品種を占めており、その普及率の高さが伺えます。 - トウモロコシ (Corn)
トウモロコシは215種類もの遺伝子組み換え品種が商業化されており、害虫抵抗性、除草剤耐性、高リシン形質、乾燥耐性、耐熱性α-アミラーゼ産生、生産性向上などの多様な特性が付与されています。具体的には、害虫抵抗性(Btトキシン)と除草剤耐性(グルホシネート、グリホサート)を併せ持つBt11、E176、MON810といった品種が挙げられます。世界で栽培されているトウモロコシのおよそ3割がGM品種であり、飼料や加工食品の原料として広く利用されています。 - ワタ (Cotton)
ワタは48種類の遺伝子組み換え品種があり、主に害虫抵抗性と除草剤耐性が付与されています。世界で栽培されているワタのおよそ8割がGM品種を占めており、農薬使用量の削減に大きく貢献しています。 - ナタネ (Canola)
ナタネには24種類の遺伝子組み換え品種が存在し、除草剤耐性が主な特性です。その他、雄性不稔性、稔性回復性、さらにはDHA産生やEPA産生といった、栄養価を高める特性を持つ品種も開発されています。 - テンサイ (Sugar Beet)
テンサイは3種類の遺伝子組み換え品種があり、除草剤耐性が主な特性として利用されています。これにより、効率的な雑草管理が可能となり、生産コストの削減に寄与しています。 - ジャガイモ (Potato)
ジャガイモは12種類の遺伝子組み換え品種が商業化されており、害虫抵抗性、ウイルス抵抗性、疫病抵抗性、アクリルアミド産生低減、打撲黒斑低減といった特性を持ちます。特に、ゲノム編集技術により天然毒素(ソラニンなど)の産生を低減する研究も進められています。ジャガイモはゲノムが複雑な四倍体であるため、従来の交配育種が困難を極めることが知られていますが、ゲノム編集はこの育種の壁を克服する大きな利点を提供しています。 - アルファルファ (Alfalfa)
アルファルファは5種類の遺伝子組み換え品種があり、除草剤耐性や低リグニンといった特性が付与されています。主に飼料作物として利用され、除草剤耐性により栽培管理が容易になり、低リグニン化により飼料としての消化性が向上します。 - パパイヤ (Papaya)
パパイヤは1種類の遺伝子組み換え品種が商業化されており、パパイヤリングスポットウイルス(PRSV)への抵抗性が主な特性です。PRSVはパパイヤに感染すると、果実に輪点を作り、生育遅延や収量低下を引き起こす壊滅的な病気であり、GMパパイヤはこの病害から産地を救う解決策として開発されました。この事例は、遺伝子組み換え技術が単なる効率化やコスト削減だけでなく、特定の地域における壊滅的な農業被害の克服にも貢献していることを示しています。これにより、食料供給の安定性が根本的に改善される可能性が示唆されます。
注目の遺伝子組み換え食品と最新の開発動向

遺伝子組み換え技術は進化を続けており、農業生産の効率化だけでなく、消費者の利便性や健康に資する新しい特性を持つ食品の開発も進められています。
変色しないリンゴ(アークティックアップル)
カナダのOkanagan Specialty Fruits社によって開発された「Arctic Apple®」は、皮をむいても変色しない遺伝子組み換えリンゴです。従来のリンゴは、果肉に含まれるポリフェノール類がPPO酵素により酸化されることで切り口が茶色く変色しますが、このGMリンゴはRNAi技術を用いてPPO酵素の働きを抑えることで褐変を防ぎます。
この技術のメリットとしては、皮をむいても変色しないため、リンゴ本来の風味が長持ちし、抗酸化物質が損なわれない点が挙げられます。米国とカナダで安全性評価の申請が行われ、米国食品医薬品局(FDA)の承認を経て、2015年5月にはArctic GoldenとArctic Grannyの2品種が市場に出回るようになりました。また、カナダ保健省も2018年にArctic Fuji Apple系統NF872の販売を認可しています。しかし、一部の農家や農業協議会からは、環境への影響を懸念する声も上がっています。
日持ちするトマト(フレーバーセーバー)の歴史と現状
フレーバーセーバー™(Flavr Savr™)は、1980年代にアメリカ・カリフォルニア州のカルジーン社が開発した遺伝子組み換えトマトです。商業的に栽培された遺伝子組み換え食品として世界で初めてヒトへの摂取許可を取得した画期的な製品であり、その歴史的意義は大きいと言えます。
このトマトは、完熟した状態でも日持ちが良いのが特徴で、1994年5月には「マクレガー」というブランド名で店頭に並び、メディアを騒がせ、すぐに完売するほどの注目を集めました。しかし、その後の商業的な成功は限定的でした。Nature誌の特集記事では、このトマトがたどった経緯に触れ、遺伝子組み換え技術が当初期待された「暮らしをよりよく、自然のめぐみをより豊かにするもの」という方向へ必ずしも進んでいない理由が検証されています。この初期の経験が、その後の遺伝子組み換え作物の開発が、害虫抵抗性や除草剤耐性といった農業生産効率に直結する特性に焦点を移すきっかけの一つとなりました。
フレーバーセーバートマトの限定的な成功と、アークティックアップルのような消費者利益型のGM食品がより最近になって市場に浸透しようとしている状況は、消費者利益型GM食品の商業化が、単に「有用な特性」を持つだけでなく、市場受容性と技術成熟度の複雑な相互作用に大きく左右されることを示しています。初期の経験から学び、技術が成熟するにつれて、より市場に受け入れられやすい特性が開発されるようになったと考えられます。
その他のユニークなGM食品事例と最新技術(ゲノム編集)

現在も様々なユニークな遺伝子組み換え食品が開発されています。例えば、ピンク色のパイナップル、がんのリスクを低減するという紫色をしたトマト、低脂肪・高オメガ3脂肪酸の油糧種子、カンキツグリーニング病への抵抗性を備えたカンキツ樹などが挙げられます。
また、遺伝子組み換え技術の進化形として、ゲノム編集技術が注目されています。これは、特定の遺伝子を狙って改変するより精密な技術であり、外部からの遺伝子導入を伴わない場合もあります。
- モチモチ食感のトウモロコシ(ワキシーコーン): ゲノム編集によって開発されたワキシーコーン品種は、従来の交配育種で作出した品種より多収になることが示されています 21。アミロペクチンをほぼ100%含むことで、加熱時に強い粘りを示すモチモチとした食感が特徴です 21。この品種は、自然界でも起こりうる突然変異を再現したものであると説明されており、社会受容性を高めるための重要なポイントとなっています。
- 天然毒素低減ジャガイモ: ジャガイモが元々持つ天然毒素(ソラニンなど)を作れないようにする研究もゲノム編集によって進められています。ジャガイモの育種の難しさ(四倍体であることなど)をゲノム編集が克服できる可能性を示しており、品質と安全性の向上に寄与すると期待されます。
ゲノム編集の台頭は、遺伝子組み換え技術の定義と社会受容性の再構築を促す可能性があります。ゲノム編集は、外部遺伝子を導入しない点で従来の遺伝子組み換えとは技術的に異なりますが、広義の「遺伝子操作」として扱われがちです。この技術の進化は、より効率的で、より予測可能で、潜在的に社会受容性の高い製品開発へとつながる可能性があり、今後の食料システムにおいてイノベーションが加速していく方向性を示しています。
遺伝子組み換え作物を原料とする加工食品
これらの作物は、直接食べるだけでなく、さまざまな加工食品の原料として使われています。
ダイズを原料とする食品
- 食用油:大豆油、サラダ油、ショートニング、マーガリンなど。
- 粉末製品:脱脂加工大豆(醤油、味噌、家畜飼料の原料)。
- 豆腐、納豆、ゆば:日本の表示制度では、遺伝子組み換え大豆を原料とする場合は表示が義務付けられています。
トウモロコシを原料とする食品
- デンプン製品:コーンスターチ、異性化糖(ブドウ糖果糖液糖)、水あめなど。清涼飲料水、菓子、パン、ビールなどの甘味料や増粘剤として広く使われています。
- 粉末製品:コーンフラワー、コーングリッツなど。スナック菓子やコーンフレーク、トルティーヤなどの原料となります。
- 食用油:コーン油。
ナタネを原料とする食品
- 食用油:キャノーラ油。
テンサイを原料とする食品
- 砂糖:テンサイ糖。
日本の表示制度における注意点
日本の食品表示制度では、遺伝子組み換え作物が使われている場合でも、精製された食用油や砂糖、醤油など、組み換えられたDNAやタンパク質が最終製品に残らないと科学的に証明された食品については、表示義務がないことがほとんどです。
このため、上記リストに挙げられた加工食品の中には、遺伝子組み換え作物を原料としていても表示がないケースが多く存在します。購入する際は、商品の表示をよく確認することが重要です。
遺伝子組み換え食品の安全性と国際的な規制
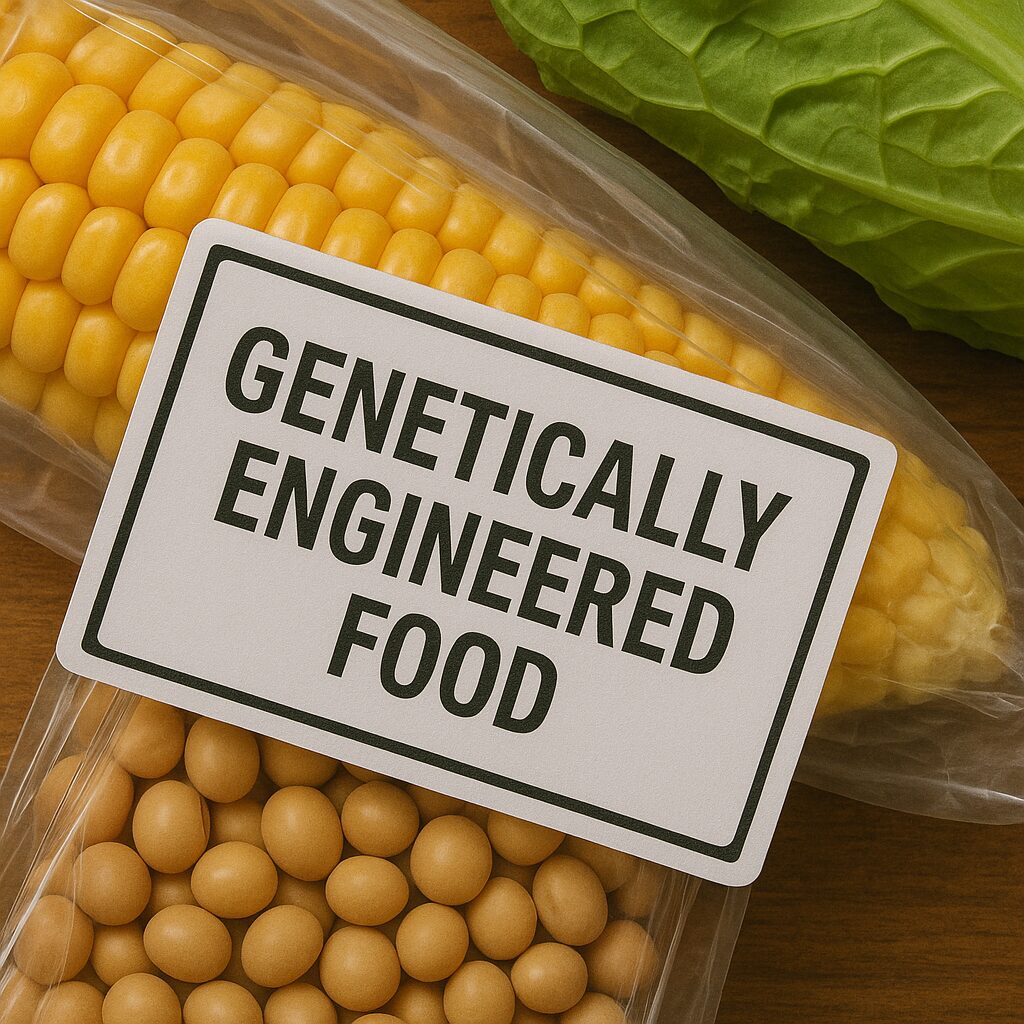
遺伝子組み換え食品の安全性については、国際的な科学的コンセンサスに基づき、厳格な評価と規制が行われています。
科学的コンセンサスと国際機関の見解
世界保健機関(WHO)と国際連合食糧農業機関(FAO)は、2001年の合同専門家会議でバイオテクノロジー応用食品の安全性評価に関する報告書を発表しており、安全性評価の一般的な手法について議論しています。
カナダ保健省(Health Canada)の遺伝子組み換え食品安全性評価手法は、WHO、FAO、経済協力開発機構(OECD)などの国際機関の専門家会議を通じて20年以上にわたり培われてきた科学的原則に立脚しています 17。この手法は、欧州連合(EU)、豪州/ニュージーランド、日本、米国といった複数の国と地域の規制機関でも採用されており、遺伝子組み換え食品の安全性評価が国際的な科学的合意に基づいた強固な枠組みを持つことを示しています。これは、承認された遺伝子組み換え食品の安全性に対する信頼性を高める重要な根拠となります。
例えば、遺伝子組み換えリンゴ「Arctic Fuji」に加えられた改変は、現在市販されているリンゴと比べ、ヒトの健康に対するリスクを増大させず、アレルギーに関する影響もなく、栄養価に差はないと結論付けられています。
日本および主要国の承認プロセスと表示制度
遺伝子組み換え作物の管理や安全性の審査、さらにそれらを利用した食品の表示等に関して、各国がそれぞれの実情に応じた法制度を設けています。
- 米国: 連邦食品・医薬品・化粧品法(FDCA)を根拠に、食品医薬品局(FDA)が安全性を確認します。米国農務省(USDA)も審査に関与しています。
- カナダ: カナダ食品検査庁(CFIA)が輸入、環境中での利用、品種登録、飼料利用に関する安全性を審査し、カナダ保健省(HC)が食品としての安全性を科学的に評価します。
- EU: 欧州食品安全機関(EFSA)が科学的観点から安全性を評価し、欧州委員会の健康・消費者保護総局(DG Sante)が規制や政策を決定します。
- オーストラリア・ニュージーランド: オーストラリア・ニュージーランド食品基準局(FSANZ)が評価等を実施し、最終承認はオーストラリア・ニュージーランド食品基準審議会(ANZFSC)が行います。
- 日本: 遺伝子組み換え農作物・食品を日本に輸入するためには、生物多様性影響評価、食品や飼料としての安全性の評価など、利用目的により必要な承認を取らなければ、商品として流通できません。
科学的合意にもかかわらず、各国の遺伝子組み換え食品に対する規制の多様性は、安全性以外の要素(公衆の受容性、環境懸念など)が意思決定に影響を与えていることを示唆します。もし安全性が唯一の懸念事項であれば、国際的な科学的合意があれば単一の承認プロセスで十分なはずです。しかし、実際には各国が独自の規制を維持していることは、環境への影響(リンゴに関する一部農家の懸念など)や消費者の受容性、社会経済的要因といった、科学的なリスク評価だけでは測れない要素が、遺伝子組み換え食品の承認と流通における意思決定に影響を与えていることを示唆しています。これは、遺伝子組み換え食品の課題が純粋な科学的側面だけでなく、社会科学的側面も含む複雑なものであることを浮き彫りにします。
以下に、2024年における遺伝子組み換え作物の栽培面積トップ国を示します。
表2:世界の遺伝子組み換え作物栽培面積トップ国(2024年)
| 順位 | 国名 | 栽培面積(万ha) | 栽培作物(主要なもの) |
| 1 | アメリカ | 7,535.9 | トウモロコシ、ダイズ、ワタ、アルファルファ、ナタネ、サトウキビ |
| 2 | ブラジル | 6,788.3 | ダイズ、トウモロコシ、ワタ、サトウキビ |
| 3 | アルゼンチン | 2,384.9 | ダイズ、トウモロコシ、ワタ、アルファルファ、コムギ |
| 4 | カナダ | 1,166.5 | ナタネ、トウモロコシ、ダイズ、テンサイ |
| 5 | インド | 1,121.0 | ワタ |
| 6 | パラグアイ | 437.8 | ワタ、トウモロコシ、ダイズ |
| 7 | 中国 | 350.7 | ワタ |
| 8 | 南アフリカ | 347.3 | トウモロコシ、ダイズ、ワタ |
| 9 | パキスタン | 190.0 | ワタ |
| 10 | ボリビア | 179.5 | ダイズ |
| 11 | ウルグアイ | 151.3 | ダイズ、トウモロコシ |
| 12 | オーストラリア | 141.2 | ナタネ、ワタ |
| 13 | フィリピン | 70.9 | トウモロコシ |
| 14 | ベトナム | 42.5 | トウモロコシ |
| 15 | スーダン | 19.6 | ワタ |
| 16 | ミャンマー | 19.0 | ワタ |
| 17 | コロンビア | 15.0 | トウモロコシ、ワタ |
遺伝子組み換え食品がもたらすメリットと課題
遺伝子組み換え食品は、農業、経済、環境、社会に多角的な影響を及ぼしており、そのメリットと課題をバランスよく理解することが重要です。
メリット:生産性向上、食料安定供給、環境負荷低減など
遺伝子組み換え作物の栽培は、安定的な収量をもたらし、農薬の費用や防除作業を減らすことで、農家の低コスト化・省力化に貢献します。2016年には、遺伝子組み換え作物による直接の農業所得は世界全体で182億ドル増加し、1ヘクタール当たり平均102ドルの所得増加に相当しました。特に発展途上国の農業従事者は、遺伝子組み換え作物への1ドル投資につき5.06ドルを受け取っており、先進国の2.70ドルを上回る利益を得ています。この経済的恩恵は、従来の農業が直面していた病害虫や雑草の問題を根本的に解決することで、収穫の安定化とコスト削減を実現し、結果として農家の収入を劇的に改善しています。特に資源が限られる発展途上国において、この経済的恩恵は貧困削減や食料安全保障に直結する、まさに農業生産のあり方を変えるほどのパラダイムシフトをもたらしていると言えます。
環境面では、遺伝子組み換え作物の栽培は、殺虫剤の使用量を大幅に削減し、1996年から2016年の間に環境影響を18.4%減少させることができました。これは、対象となる害虫以外への影響が少なく、環境に残留しない特性によるものです。
食料安全保障への貢献も大きなメリットです。効率的な品種改良と安定した収量は、増大する世界人口に持続可能な方法で食を提供し、飢餓や貧困問題の解決に貢献する可能性を秘めています。また、変色しないリンゴ、日持ちするトマト、高オレイン酸大豆、DHA/EPA産生ナタネ、天然毒素低減ジャガイモなど、消費者の利便性や健康に資する特性を持つ作物の開発も進んでいます。
課題:環境影響、社会受容性、多様性への懸念など
一方で、遺伝子組み換え食品にはいくつかの課題も指摘されています。
- 環境への懸念:
- 除草剤に強い雑草の発生: 除草剤耐性遺伝子組み換え作物の普及により、除草剤に抵抗性を持つ雑草が出現する可能性があります。
- 病害虫の抵抗性獲得: 遺伝子組み換え作物に耐性を持った病害虫が現れ、他の作物に被害を及ぼす危険性も指摘されています。ブラジルでは、遺伝子組み換え作物に抵抗性を持った病害虫が現れ、政府が承認していない殺虫剤を散布した例も報告されています。
- 在来種の遺伝子汚染・多様性の喪失: 遺伝子組み換え作物が在来の作物と同じ農地で栽培されると、交雑によって在来種の遺伝子が置き換わったり、遺伝子組み換え作物の繁殖力が強いために在来の作物の栽培が難しくなったりする懸念があります。
- 周辺生物への影響: 周辺の生物に害を与え、死滅させる可能性も指摘されています。
- 安全性への懸念と社会受容性:
- アレルギーのリスク: 遺伝子組み換え食品がアレルギーを引き起こす原因になる可能性が指摘されています。
- 長期的な影響の不明確さ: 科学的な安全性評価が行われている一方で、「安全性は不明確な部分が多い」として、生態系や健康への長期的な影響について継続的な研究の必要性を訴える声もあります。
- 倫理的・社会的な批判: 遺伝子操作に批判的な人々からの受容が得られにくいという意見や、バイテク・種子会社の歩んだ道筋や反対派が発信する情報が社会受容性に影響を与えているという指摘もあります。
- 経済的・社会的不均衡: Nature誌の論説では、遺伝子組み換え技術の商業化に向けた開発が極めて急速に行われてきたため、多くの研究が「利益を生む分野に限定されてきた」と指摘されており、これが技術の約束された進歩を妨げている可能性が示唆されています。
遺伝子組み換え食品の安全性に関する議論は、単に「食べても大丈夫か」という狭義の科学的リスク評価を超えて、環境への影響、倫理的配慮、企業の支配力、長期的な社会経済的影響といった、より広範で複雑な懸念へと拡大しています。この多層的な課題の存在が、遺伝子組み換え食品の社会受容性を左右する大きな要因となっています。
まとめ:遺伝子組み換え食品の未来と私たちの選択
遺伝子組み換え食品・一覧に関する本レポートでは、遺伝子組み換え食品の定義から、世界で商業化されている主要な作物、注目の開発動向、安全性と規制、そしてメリットと課題に至るまで、多角的な側面からその実態を解説しました。
遺伝子組み換え食品は、他の生物の遺伝子を組み込むことで特定の有用な性質を付与された食品であり、その開発目的は、除草剤耐性や害虫抵抗性による農業効率の向上から、消費者の利便性や栄養価向上まで多岐にわたります。ダイズ、トウモロコシ、ワタ、ナタネといった主要作物から、変色しないリンゴや天然毒素低減ジャガイモといった消費者利益型の製品まで、その種類と特性は多様です。
安全性については、世界保健機関(WHO)や国際連合食糧農業機関(FAO)などの国際機関が確立した科学的原則に基づき、各国で厳格な評価と規制プロセスを経て承認された遺伝子組み換え食品は、安全性が確認されています。しかし、環境影響、社会受容性、倫理的側面など、科学的安全性評価を超えた複合的な課題が依然として存在し、継続的な議論と研究が必要です。
ゲノム編集のような新しい技術の登場は、より精密で多様な特性を持つ作物の開発を可能にし、食料生産におけるイノベーションの加速と精密化の方向性を示しています。この進化は、より効率的で、より予測可能で、潜在的に社会受容性の高い製品開発へとつながる可能性を秘めています。増大する世界人口への食料供給、環境負荷の低減といった地球規模の課題解決において、遺伝子組み換え技術は重要なツールの一つであり続けるでしょう。
遺伝子組み換え食品に対する社会の認識がしばしば二極化している現状において、本レポートが、遺伝子組み換え食品の定義、具体的なリスト、安全性、メリット、課題といった多角的な側面を包括的に提示したことは、社会的な対話と意思決定の質を高める上で不可欠です。消費者としては、科学的根拠に基づいた情報と、多角的な視点からメリットと課題を理解し、感情的な反応ではなく、自身の価値観に基づいて賢明な選択をすることが求められます。









