ニパウイルス感染症・日本

ニパウイルス感染症・日本
ニパウイルス感染症と日本の対応について
近年、南アジアを中心に発生しているニパウイルス感染症(Nipah virus infection)が国際的に注目されています。致死率が非常に高く、人から人への感染も報告されていることから、日本でも関心が高まっています。本記事では、日本におけるニパウイルス感染症の位置づけや対応、渡航者への注意点について解説します。
ニパウイルス感染症とは
ニパウイルスはオオコウモリを自然宿主とし、果物や樹液、家畜(特に豚)を介して人に感染します。症状は発熱や頭痛から始まり、重症化すると脳炎や呼吸不全を引き起こし、致死率は40〜75%と極めて高いことで知られています。現在、有効な治療薬やワクチンは確立されておらず、対症療法が中心です。
日本での位置づけ
日本では、ニパウイルス感染症は 感染症法に基づく4類感染症 に指定されています。これにより、医師が疑われる症例を診断した場合、直ちに最寄りの保健所に届け出る義務があります。また、国立感染症研究所が中心となり、検査体制の整備や情報提供が行われています。
さらに、厚生労働省は海外での流行状況を踏まえ、検疫所を通じた監視を強化しています。渡航者からの持ち込みを防ぐことが、日本国内での感染拡大を防ぐ上で重要です。
日本でのリスクと現状
国内での発生は?
これまでのところ、日本国内でニパウイルス感染症の患者が確認された事例はありません。ただし、国際的な人の往来が活発な現代において、海外からの持ち込みリスクは常に存在しています。
リスクが高い場面
- インドやバングラデシュなどの流行地域への渡航
- 現地での生の果物や樹液の摂取
- 家畜やコウモリとの接触
こうした行動が感染リスクを高める可能性があります。
日本の対策
1. 検疫体制の強化
空港や港において、流行地域からの渡航者に対して健康状態の確認や検疫を実施しています。
2. 医療機関への情報提供
医療機関に対し、感染が疑われる症例の特徴や対応方法を周知することで、早期発見と迅速な隔離を可能にしています。
3. 研究とワクチン開発への参加
国際的な枠組みに参加し、ワクチンや治療薬の研究に貢献しています。日本国内でもワクチン候補の臨床試験に関する情報が共有されています。
渡航者への注意点
ニパウイルスの流行地へ渡航する場合、以下の点に注意が必要です。
- 🍌 生の果物やコウモリが触れた可能性のある食品は避ける
- 🐖 豚などの家畜に近づかない
- 🙌 こまめな手洗いと衛生管理を徹底する
- 🤒 発熱や頭痛などの症状が出た場合は速やかに医療機関を受診し、渡航歴を伝える
ニパウイルス感染症は日本国内では確認されていないものの、海外での流行や国際的な移動を背景に常に警戒が必要な感染症です。厚生労働省や国立感染症研究所が中心となり、監視体制と情報提供が進められています。渡航者自身も、食品や動物との接触を避けるといった予防行動を心がけることが重要です。
最新動向:ニパウイルスの法的分類が強化
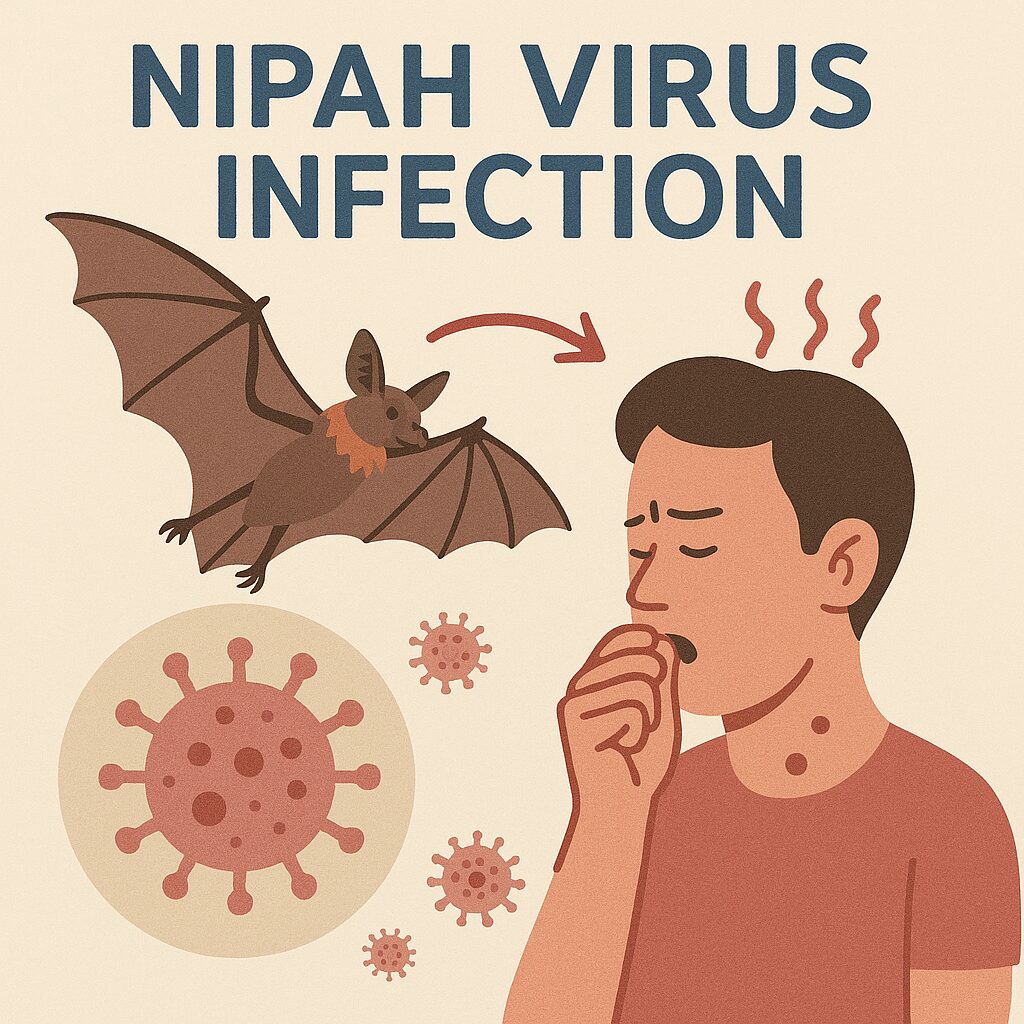
2025年9月8日、韓国の疾病管理庁が ニパウイルス感染症を「第1級感染症」に追加 しました。これは、重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)と同様に、非常に高い致死率や集団発生のリスクを理由に定められる最高レベルの指定です。これにより、診断から報告、隔離措置までの体制が強化されました。
昨年(2024年)にはWHOがニパウイルスを「国際公衆衛生上の緊急対応が必要な病原体候補」に位置づけています。
過去の主なアウトブレイクと現状
歴史的流行
- 1998~1999年(マレーシア):養豚場を起点に急性脳炎の流行が発生。豚からヒトへの感染が確認され、多数の死者を出しました。これが「ニパウイルス」の命名のきっかけとなりました。
- その後:インドやバングラデシュではほぼ毎年小規模な流行が発生し、人から人への感染も確認されています。
2023年のインド・ケララ州
- 2023年9月12日~15日:**6症例(うち2人死亡)**を確認。すべて男性で、濃厚接触者1,288人が追跡され隔離措置を実施。
- ウイルスはインド・バングラデシュ型と関連があると報告されました。
バングラデシュでの2023年流行
- **11人感染、8人死亡(致死率約73%)**と報告され、過去7年間で異例の規模でした。
特徴と予防ポイント
- 致死率:40~75%と高く、報告によってはさらに高いケースもあります。
- 感染経路:自然宿主はオオコウモリ。コウモリの唾液や尿が付着した果物や樹液、家畜(豚や馬)を介して感染。人から人への感染も確認。
- 症状:発熱、頭痛、筋肉痛、嘔吐、呼吸器症状、意識障害、痙攣、脳炎など。重症化すると昏睡状態に至ることも。
- 治療・ワクチン:現時点では有効な治療法やワクチンは確立されていません。対症療法が中心。mRNAやChAdOx1ベースのワクチン候補の臨床試験が進行中。
日本への影響
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 話題になっている背景 | 韓国が2025年9月に第1級感染症に指定 |
| 主な流行地 | 南アジア(インド、バングラデシュ)、東南アジア |
| 致死率 | 40~75% |
| 感染経路 | コウモリ→家畜→ヒト、食品由来、人から人への感染も報告 |
| 治療・ワクチン | 未確立、対症療法のみ、ワクチン開発中 |
| 日本へのリスク | 現時点で報告なし。厚労省では4類感染症に指定。渡航時は十分注意が必要 |
Q&Aコーナー

Q1. ニパウイルス感染症が日本に入ってきた場合、人から人へ感染しますか?
A. はい、ニパウイルスは人から人への感染が報告されています。ただし、持続的な大規模感染は限定的で、主に濃厚接触によるケースが中心です。医療従事者や家族間での感染が多く見られます。
Q2. ニパウイルス感染症に対するワクチンはありますか?
A. 現時点では有効なワクチンは実用化されていません。世界的にmRNAワクチンやウイルスベクター型ワクチンの研究が進められており、臨床試験も実施されていますが、実用化には時間がかかると考えられています。
Q3. 日本で感染者が出た場合、どのように対応されますか?
A. 日本では4類感染症に指定されているため、直ちに保健所に報告され、国立感染症研究所などで検査・確認が行われます。また、必要に応じて隔離や接触者追跡が実施され、感染拡大を防ぐ体制が整えられています。
Q4.ニパウイルス感染症は、インフルエンザのように空気感染しますか?
A. インフルエンザのような飛沫感染や空気感染による大規模な伝播は確認されていません。主に、感染者の体液(唾液、血液、尿など)との直接的な接触や、汚染された表面を触れた後に口や鼻に触れることによる接触感染が報告されています。しかし、リスクを避けるため、感染が疑われる患者と接する場合は、マスクや手袋の着用などの基本的な感染対策が重要です。
Q5. なぜコウモリがウイルスを保有しているのに、病気にならないのですか?
A. オオコウモリは、ニパウイルスを含む多くのウイルスを体内に持ちながら、自身は発症しない「自然宿主」と考えられています。これは、コウモリが持つユニークな免疫システムに関係していると推測されています。コウモリの体温が飛行中に上昇しても、免疫システムがウイルスを効率よく抑制する能力を持っているため、ウイルスは体内で増殖しますが、コウモリは病気にならないと考えられています。
Q6. 渡航中に感染した場合、どのように帰国すればいいですか?
A. 海外でニパウイルス感染症の症状(高熱、頭痛など)が出た場合は、まず現地の医療機関をすぐに受診し、渡航歴を正確に伝えてください。その上で、日本の検疫所や在外公館(大使館、領事館)に連絡し、指示を仰ぐことが重要です。帰国時には、感染拡大を防ぐため、検疫所と連携した特別な対応が必要となります。個人の判断で帰国便を手配するのではなく、必ず専門機関の指示に従いましょう。










